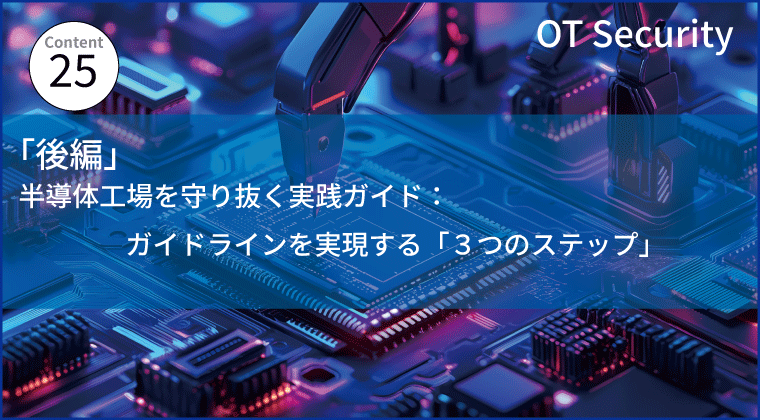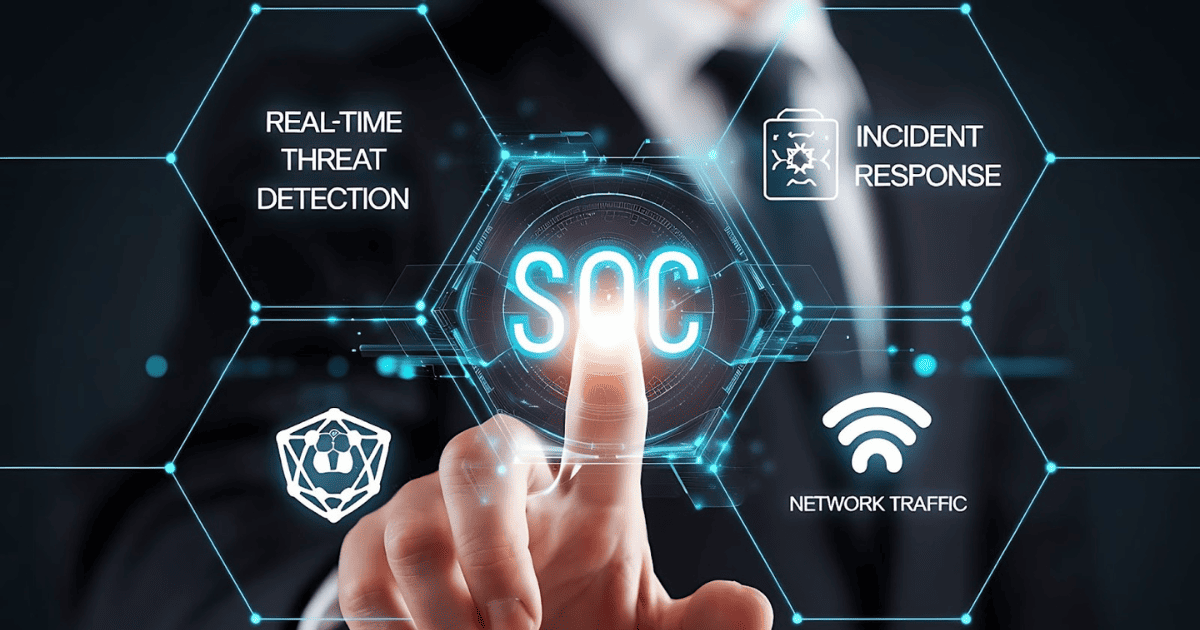
SOC(Security Operation Center)とは?企業のセキュリティの監視と対応を担う中枢機能
SOCの定義と役割
SOCとは、企業のIT資産をサイバー攻撃から守るため、以下のような業務を専門的に担うセキュリティ監視・対応の組織・機能です。
- セキュリティイベントの常時監視
- 脅威の分析とインシデントの検知
- 迅速な対応支援と被害の最小化
ファイアウォール、IDS/IPS、EDRなどさまざまなセキュリティ機器やシステムからログを収集・相関分析し、組織全体のセキュリティ状況を可視化。潜在的な脅威をプロアクティブに特定し、インシデント対応チームのCSIRT(Computer Security Incident Response Team)と連携して対応を行います。
SOCが担う主な業務内容
SOCの業務は多岐にわたりますが、主な業務は以下の通りです。
項目 | 内容 |
|---|---|
リアルタイム監視とログ分析 | SIEM(Security Information and Event Management)などを活用し、24時間365日体制でログを監視。不審な挙動や攻撃の兆候を検知。 |
インシデント検知とトリアージ | アラートの真偽を判断し、深刻度・影響範囲・緊急性を評価。 |
インシデント対応支援 | 封じ込め・駆除・復旧までを支援し、関係部署と連携。 |
脅威インテリジェンスの活用 | 最新の攻撃手法や脆弱性情報をもとに、監視ルールを最適化。 |
レポート作成と報告 | 監視状況、インシデント対応結果、脅威傾向を経営層へ報告し対策改善に活用 |
なぜ今SOCが必要とされるのか?
日々深刻化・巧妙化するサイバー攻撃の脅威
サイバー攻撃は日々進化し、新たな技術や戦術を取り入れながら巧妙さを増しています。IPA「情報セキュリティ10大脅威 2025」によると、ランサムウェアやサプライチェーン攻撃、内部不正など、組織を狙う脅威は年々多様化・高度化しています。これらの攻撃は、検知が遅れると情報漏えいや業務停止といった深刻な被害をもたらします。
情報セキュリティ10大脅威 2025 [組織]
順位 | 「組織」向け脅威 | 初選出年 | 10大脅威での取り扱い(2016年以降) |
|---|---|---|---|
1 | ランサム攻撃による被害 | 2016年 | 10年連続10回目 |
2 | サプライチェーンや委託先を狙った攻撃 | 2019年 | 7年連続7回目 |
3 | システムの脆弱性を突いた攻撃 | 2016年 | 5年連続8回目 |
4 | 内部不正による情報漏えい等 | 2016年 | 10年連続10回目 |
5 | 機密情報等を狙った標的型攻撃 | 2016年 | 10年連続10回目 |
6 | リモートワーク等の環境や仕組みを狙った攻撃 | 2021年 | 5年連続5回目 |
7 | 地政学的リスクに起因するサイバー攻撃 | 2025年 | 初選出 |
8 | 分散型サービス妨害攻撃(DDoS攻撃) | 2016年 | 5年ぶり6回目 |
9 | ビジネスメール詐欺 | 2018年 | 8年連続8回目 |
10 | 不注意による情報漏えい等 | 2016年 | 7年連続8回目 |
出典:IPA「情報セキュリティ10大脅威 2025 [組織]」を基に作成
https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2025.html
見過ごされがちな攻撃が事業継続に与える影響
サイバー攻撃の中には、通常の通信と見分けがつかないほど巧妙なものも存在します。こうした攻撃の検知が遅れれば、内部ネットワークへの侵入を許し、長期間にわたって潜伏・情報窃取・システム破壊といった活動を行われるリスクがあります。インシデントの検知や対応が遅れると、以下のような深刻な影響を及ぼす可能性があります。
- 業務停止やサービス中断による売上損失
- 顧客情報の漏えいによる信用失墜
- 法的責任や罰則の発生
- 株価の下落やブランドイメージの毀損
このようなリスクを最小限に抑えるためには、常時監視体制の構築と迅速な対応力の確保が不可欠です。
ログ監視の重要性と直面する課題
サイバー攻撃の兆候は、ネットワーク機器やサーバー、PCなどから出力される膨大なログを継続的に監視することが不可欠です。しかし、現代のIT環境では以下のような課題が存在します。
- 膨大なログ量
数百万件単位のログが日々生成されるため、人手による監視は現実的ではありません。 - アラートの過多
SIEMなどのツールから大量のアラートが発生し、本当に重要な兆候を見逃すリスクがあります。 - 専門知識の必要性
ログの相関分析や脅威の特定には高度なスキルが求められ、対応できる人材の確保が困難です。
これらの課題を解決するために、SOCのような専門組織による体制整備が求められています。
SOCの主な機能と業務内容
SOCは、サイバー攻撃から企業を守るために多様な機能を担っています。ここでは、SOCが持つ3つの主要な機能と、それぞれに関連する具体的な業務内容について詳しく解説します。
インシデント検知・対応
SOCの最も重要な機能は、セキュリティインシデントを早期に検知し、被害を最小限に抑えるための対応を行うことです。
- 監視対象のシステムから異常な挙動や攻撃の兆候を示すアラートを検知すると、その内容を詳細に分析します。
- アラートが誤検知か真の脅威かを判断する「トリアージ」を実施し、インシデントと判断された場合は、管理者への迅速な報告や、通信遮断などの一次対応を実施します。
- 必要に応じて、CSIRTや関係部署と連携し、封じ込め・駆除・復旧までの対応を支援します。
このプロセスにより、攻撃の拡大を防ぎ、業務への影響を最小限に抑えることが可能になります。
ログの収集・分析
SOCは、企業内のIT環境に存在する多様な機器から出力されるログを一元的に収集・保管し、相関分析を行います。
- 対象となるログには、ファイアウォール、IDS/IPS、EDR、サーバー、PCなどからの情報が含まれます。
- これらのログをSIEMなどのツールを用いて相関分析し、単一のログだけでは見逃されがちな攻撃の痕跡やセキュリティリスクを浮かび上がらせます
- 継続的なログ分析により、過去の傾向や異常パターンを把握し、将来的なリスクの予測や監視ルールの改善にもつなげることができます。
このように、ログ分析はSOCの中核的な業務であり、脅威の可視化と早期発見の鍵となります。
脅威インテリジェンスの活用
SOCでは、外部から得られる最新の脅威情報(脅威インテリジェンス)を活用し、監視体制の強化を図ります。
- 脅威インテリジェンスには、攻撃者の手法、マルウェアの挙動、新たな脆弱性情報が含まれます。
- これらの情報をもとに、SIEMの検知ルールやロジックを最適化し、未知の攻撃に対する検知能力を高めます。
- また、業界横断的な情報共有(ISACなど)を通じて、他社の事例や傾向を自社の対策に反映させることも可能です。
このように、脅威インテリジェンスの活用は、SOCの対応力を継続的に進化させるための重要な要素です。
SOCとCSIRT、SIEMの違い
SOCを理解するためには、しばしば混同されがちなCSIRTやSIEMとの違いを明確にすることが重要です。それぞれの役割と関係性を理解することで、自社のセキュリティ体制におけるSOCの位置づけがより明確になります。
用語 | 種別 | 主な役割 |
|---|---|---|
SOC | 組織・機能 | セキュリティインシデントの検知・分析に特化。「見つける」ことが主目的。 |
CSIRT | 組織・機能 | インシデント発生後の対応に特化。「対処する」ことが主目的。 |
SIEM | ツール | ログを収集・分析し、脅威を可視化するためのプラットフォーム。SOCが利用する主要な道具。 |
SOCとCSIRTの違い
SOCとCSIRTは連携して活動しますが、役割に明確な違いがあります。
- SOCはインシデントの「検知」と「分析」を主に行う技術的なチームであり、日々の監視業務を通じて脅威を発見します。
- 一方、CSIRTは、SOCから報告を受け、インシデントの封じ込め・根本原因の調査・再発防止策の策定など、全社的な「対応」を指揮・調整するチームです。
- CSIRTは広報、法務、経営層などとも連携し、インシデント対応の司令塔となります。
関連記事:【5分でわかる】SOCとCSIRTの違いを徹底解説!自社に最適なセキュリティ体制とは
SOCとSIEMの違い
SOCとSIEMの関係は、「料理人」と「調理器具」に例えられます。
- SIEMは、膨大なログを効率的に収集・分析し、脅威を可視化するための「ツール(プラットフォーム)」です。
- SOCは、そのSIEMを使いこなし、脅威を発見・分析する「専門家チーム(組織)」です。
SIEMを導入するだけでは不十分で、それを運用するSOCがあってこそ、セキュリティ対策としての効果が発揮されます。
関連記事:SOCとSIEMの違いを5分で理解|役割分担と連携のポイントを解説
SOC導入のメリット・デメリット
SOCを導入することは、セキュリティレベルの向上やインシデント対応の迅速化など、企業に多くのメリットをもたらす一方で、導入・運用コストや人材面での課題も伴います。ここでは導入前に理解しておくべきメリット・デメリットを整理します。
メリット | デメリット |
|---|---|
- セキュリティ体制の強化 | - 高額な導入・運用コスト |
- インシデント対応の迅速化 | - 専門人材の確保の難しさ |
- コンプライアンス対応の支援 | - 内製と外注の選択 |
SOC運用における現実的な課題と限界
SOCの導入・運用を検討する上で、多くの企業が直面する主な課題は以下の3点です。
高度な専門人材の確保と維持の難しさ
SOCの運用には、ログ分析や脅威検知に関する高度な知識と経験を持つアナリストが不可欠です。しかし、こうした人材は市場でも希少であり、採用競争が激化しています。また、採用後も継続的な教育やモチベーション維持が必要で、人材マネジメントの負担は非常に大きくなります。
高額な初期投資と継続的な運用コスト
SIEMや脅威インテリジェンスフィードなどの導入には初期投資が必要です。さらに24時間体制を維持するための人件費やシステム保守費、施設運用費など、継続的なコスト負担も無視できません。費用対効果を慎重に見極める必要があります。
24時間365日体制の構築・維持の負担
サイバー攻撃は時間を選ばず発生するため、SOCは常時稼働が求められます。これを自社で実現するには、シフト勤務が可能な8〜10名程度の専門スタッフが必要となり、採用、教育、労務管理の負担が非常に大きくなります。
自社に最適なセキュリティ体制を築くために
これらの課題を踏まえ、すべての企業が自社でSOCを構築・運用(内製)することが最適解とは限りません。自社の規模やリスク、予算に応じて以下のような選択肢を検討することが必要です。
SOC構築・運用(内製化)を検討すべき企業の特徴
下記のような企業では、内製SOCによって柔軟かつ高度なセキュリティ運用が可能になります。
- 機密性の高い情報を多く扱う企業(例:金融機関、政府機関、大手製造業など)
- 独自のセキュリティポリシーやインシデント対応プロセスが必要な企業・組織
- セキュリティ対策に十分な予算確保と人材投資ができる体力がある企業
SOC運用の課題を解決するMDRという選択肢
SOCの内製化に伴う「コスト」と「人材」の課題を解決する現実的な選択肢として、MDR(Managed Detection and Response)サービスが注目されています。
- MDRは、SOCの機能である脅威の検知・分析・対応を、外部の専門チームが提供するアウトソーシングサービスです。
- 自社でSOCを構築・運用する必要がなく、高度なセキュリティ監視体制を短期間かつ低コストで導入可能です。
- 最新の脅威インテリジェンスやAI技術を活用した分析が行われるため、未知の攻撃にも迅速に対応できます。
MDRとSOCの違いを理解し、最適な対策を選ぼう
MDRは、SOCの機能を包括しつつ、より即応性の高いセキュリティ運用を実現するサービスです。一方、SOCは自社内でのセキュリティ監視体制の中核として、継続的な監視と初動対応を担う組織的機能です。自社の目的や課題に応じて、これらの違いを理解し、最適な対策を選択することが重要です。
関連記事:【徹底比較】MDRとSOCの違いとは?自社に最適な選び方を解説
まとめ:SOCを理解し、最適なセキュリティ対策を実施しましょう
本記事では、SOCの基本的な役割から導入によるメリット・デメリット、そして運用上の課題までとその解決策までを解説しました。SOCは、巧妙化・高度化するサイバー攻撃から企業を守るためのセキュリティ監視の中核を担う重要な存在です。24時間365日の体制でログを監視し、脅威を早期に検知・分析・対応することで、企業の情報資産と事業継続性を守ります。
しかし、その運用には高度な専門知識を持つ人材の確保や、継続的なコスト負担といった課題も伴います。そのため、すべての企業にとってSOCの内製化が最適とは限りません。自社の事業規模、リスクレベル、予算、そしてセキュリティに対する戦略的な優先度を踏まえたうえで、以下のような選択肢を柔軟に検討することが重要です。
- 自社でSOCを構築・運用する「内製型」
- より実践的な対応力を備えた「MDR(Managed Detection and Response)」
これらの選択肢を適切に組み合わせることで、自社に最適なセキュリティ体制を構築し、持続的なビジネス成長と信頼性の確保につなげることができます。
【ホワイトペーパー】
人材不足・複雑化する脅威にどう立ち向かう?
MDRアウトソーシングで乗り越えるセキュリティ運用の壁
ダウンロード