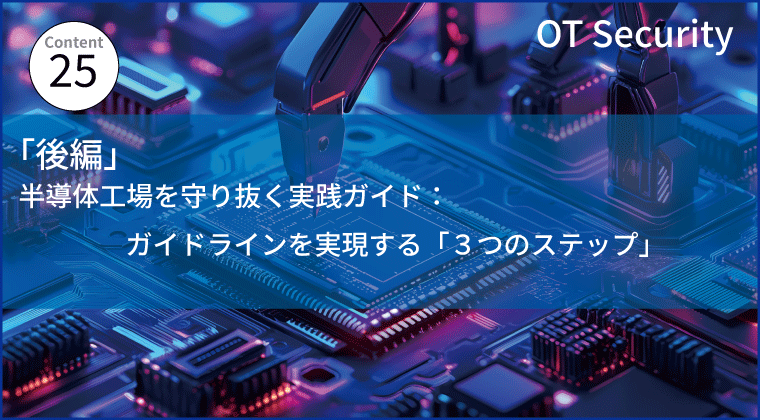本記事では、EDRとSIEMの基本的な知識から、明確な違い、連携によるメリット、そして導入のポイントまでをわかりやすく解説します。
最新の脅威にどう対応する? EDRとSIEMの役割
IPA「情報セキュリティ10大脅威 2025」で報告されている通り、昨今の企業が直面するリスクは多様化しています。ここでは、上位の脅威に対する、EDRとSIEMの対応力を見ていきましょう。
ランサムウェア対策の要: EDR
ランサムウェア攻撃は、侵入後の内部活動によって被害が拡大します。EDRはエンドポイント上の異常な挙動を検知・隔離することで被害の拡大を防ぐ”最後の砦”として機能します。
サプライチェーン攻撃の備え:SIEM
取引先を経由した攻撃には、組織全体のログを横断的に監視するSIEMが有効です。多様なシステムからログを収集・分析し、普段とは異なる通信やアクセスのパターンから、攻撃の兆候を早期に発見できます。
内部不正の抑止と発見:SIEM
従業員など内部関係者による情報漏えいも深刻な脅威です。SIEMは、従業員のPC操作やファイルサーバーへのアクセスログなどを監視し、「深夜の大量データダウンロード」といった異常行動を検知することで、内部不正の抑止と早期発見に貢献します。
情報セキュリティ10大脅威 2025 [組織]
順位 | 「組織」向け脅威 | 初選出年 | 10大脅威での取り扱い(2016年以降) |
|---|---|---|---|
1 | ランサム攻撃による被害 | 2016年 | 10年連続10回目 |
2 | サプライチェーンや委託先を狙った攻撃 | 2019年 | 7年連続7回目 |
3 | システムの脆弱性を突いた攻撃 | 2016年 | 5年連続8回目 |
4 | 内部不正による情報漏えい等 | 2016年 | 10年連続10回目 |
5 | 機密情報等を狙った標的型攻撃 | 2016年 | 10年連続10回目 |
6 | リモートワーク等の環境や仕組みを狙った攻撃 | 2021年 | 5年連続5回目 |
7 | 地政学的リスクに起因するサイバー攻撃 | 2025年 | 初選出 |
8 | 分散型サービス妨害攻撃(DDoS攻撃) | 2016年 | 5年ぶり6回目 |
9 | ビジネスメール詐欺 | 2018年 | 8年連続8回目 |
10 | 不注意による情報漏えい等 | 2016年 | 7年連続8回目 |
出典:IPA「情報セキュリティ10大脅威 2025 [組織]」を基に作成
https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2025.html
EDRとは?エンドポイントを守る”最後の砦”
EDR(Endpoint Detection and Response)は、PCやサーバーなどの「エンドポイント」に特化したセキュリティ対策です。万が一の侵入後、脅威を迅速に検知・対応、被害を最小限に食い止めることを目的とします。
EDRの主な機能と役割
EDRはエンドポイント内のあらゆる操作を記録・監視し、攻撃特有の不審な振る舞いを検知して管理者に通知します。さらに、攻撃範囲の特定や、遠隔操作による端末の隔離、不正プロセスの強制終了など、迅速なインシデント対応を支援します。
従来のアンチウイルス(EPP)との違い
従来のアンチウイルス(EPP)が、既知の脅威の侵入を防ぐ「水際対策」であるのに対し、EDRは侵入を前提とし、未知の脅威による侵入後の活動を検知・対処する点で役割が明確に異なります。
関連記事:今さら聞けない「EDR」とは?基本的な役割と導入後の運用課題をわかりやすく解説
SIEMとは?組織全体を見渡す”セキュリティの司令塔”
SIEM(Security Information and Event Management)は、組織内の様々なIT機器からログを集約・分析し、セキュリティ状況を可視化する基盤です。サイバー攻撃の兆候を早期発見するための「司令塔」と言えます。
SIEMの主な機能と役割
SIEMは、多様なログを収集・正規化して長期保管します。そして、相関分析ルールやAIを用いて複数のログを横断的に分析し、単体のログでは見つけられない高度な攻撃の兆威を検知・通知します。ダッシュボードによる状況の可視化も重要な機能です。
組織全体のログを相関分析する重要性
例えば、「不審なログイン(認証ログ)」と直後の「機密サーバーへのアクセス(サーバーログ)」は、単体では見過ごされがちです。しかし、SIEMはこれらを関連付け、「不正アクセス後の内部侵入」という一連の攻撃として検知できます。これがSIEMの相関分析の価値です。
関連記事:SIEMとは?仕組みや機能、メリットから導入・運用の課題まで徹底解説
【徹底比較】EDRとSIEMの違いを3つの観点から解説
EDRとSIEMの本質的な違いを、3つの観点から比較・解説します。例えるなら、EDRが「木(個々の端末)」を見るのに対し、SIEMは「森(組織全体)」を見るという違いを理解することが重要です。
観点 | EDR | SIEM |
|---|---|---|
監視対象 | エンドポイント(PC、サーバー等)の内部挙動 | 組織全体のITインフラのログ |
検知アプローチ | 侵入後の振る舞い検知 | ログの相関分析による兆候検知 |
主な目的 | インシデントの封じ込め・対応 | 脅威の可視化・早期発見 |
観点1:監視対象の違い(ミクロ vs マクロ)
- EDR: PCやサーバーなど、個々の「エンドポイント」の内部を深く監視します。
- SIEM: ネットワーク全体からログを集約し、組織全体を俯瞰的に監視します。
観点2:検知アプローチの違い(侵入後 vs 兆候)
- EDR: 脅威がエンドポイントに侵入し、活動を開始した「後」の不審な振る舞いを検知します。
- SIEM: 複数のログを分析し、本格的な攻撃に至る前の「兆候」を検知します。
観点3:主な目的の違い(封じ込め vs 全体把握)
- EDR: 脅威を迅速に隔離・除去し、被害を「封じ込める」ことを目的とします。
- SIEM: 組織全体のセキュリティ状況を「全体把握」し、早期発見や監査対応に活用することを目的とします。
自社にはどっち?EDRとSIEMの選び方と導入シナリオ
企業の課題によって、EDRとSIEMのどちらを優先すべきかは異なります。自社の状況に合わせた選び方の指針と、特にリソースが限られる中小企業向けの対策を解説します。
EDRの導入を優先すべき企業ケース
- テレワーク主体で外部アクセスが多い
- ランサムウェアなどエンドポイントへの攻撃を最優先で対策したい
- まずは侵入後の被害を最小化する体制を構築したい
SIEMの導入を優先すべき企業ケース
- 複数のクラウドサービスなど複雑なIT環境を持つ
- ログの長期保管や監査対応といったコンプライアンス要件が厳しい
- 内部不正対策を強化したい
導入検討時のチェックポイント
EDRやSIEMの導入を成功させるには、事前の目的設定と評価が不可欠です。以下のチェックポイントを参考に、自社の状況を整理・評価しましょう。
チェック項目 | 主な確認内容 |
|---|---|
① 導入目的の明確化 | - 保護対象: 何を保護したいのか? (例: 顧客情報、技術情報、基幹システム) |
② 既存環境との相性 | - 連携性: 現在利用中のセキュリティ製品やクラウドサービスとスムーズに連携できるか? |
③ 運用体制の構築 | - 担当者: 誰が24時間365日体制でアラートを監視し、対応するのか? |
④ 将来的な拡張性 | - 柔軟性: 事業拡大やIT環境の変化に合わせて、監視対象を柔軟に追加できるか? |
中小企業向け:導入ハードルと対策
導入コスト・人材不足・運用負荷といった課題
高価なライセンス費用や初期構築費に加え、24時間365日体制でアラートを監視・分析できる専門家の確保は、中小企業にとって容易ではありません。また、導入後も検知ルールの継続的なチューニングが必要となるなど、日々の運用負荷も大きな負担となります。
MSS(マネージドセキュリティサービス)やクラウド型EDR/SIEMの活用
上記の課題を解決する有効な手段として、MSSやクラウドサービスの活用が挙げられます。MSSを利用すれば、セキュリティ専門家チームが監視・運用を代行してくれるため、自社の「人材不足」への対応と「運用負荷」の軽減ができます。また、初期投資を抑えられる月額課金制のクラウド型EDR/SIEMを選択することで、「コスト」のハードルを大幅に下げることが可能です。
関連記事:【MSSとは?】企業のセキュリティ運用を効率化する最適な選択肢
中小企業でも安心!段階的導入と外部ベンダー活用のすすめ
全てを一度に解決しようとせず、段階的に導入を進めるアプローチも重要です。例えば、まずは最重要システムや特にリスクの高い部門からスモールスタートし、効果を見ながら適用範囲を広げていきます。その際、外部の専門ベンダーと連携し、客観的なアドバイスや技術支援を受けながら進めることで、導入の失敗リスクを低減させ、スムーズな導入が可能となります。
最強の防御体制へ。EDRとSIEMの連携が生む相乗効果
検知精度の向上と誤検知の削減
SIEMが検知した「不審な通信」と、EDRが検知した「端末上の異常な挙動」を突き合わせることで、アラートの確度が格段に向上します。これにより、対応の優先順位付けが容易になり、誤検知に振り回されるリスクを低減できます。
インシデント調査の迅速化と全体像の把握
EDRでマルウェアを検知した際、SIEMのログを遡ることで感染経路を特定できます。逆に、SIEMで不審な通信を見つけ、EDRで通信元の端末を調査することも可能です。この連携により、インシデントの全体像を迅速かつ正確に把握できます。
SOC運用における連携の重要性
SOC(Security Operation Center)のアナリストにとって、EDRとSIEMの連携は運用効率を劇的に向上させます。1つの画面上でエンドポイントからネットワークまで一貫した調査が可能になり、より高度な脅威分析に時間を割けるようになります。
ゼロトラストとの関連性:境界防御からの脱却
「信頼しないことを前提とする」セキュリティモデルの概要
ゼロトラストとは、社内外を問わず、あらゆるアクセスを「信頼せず、常に検証する」ことを前提としたセキュリティモデルです。従来の境界型防御では対応しきれない、クラウドやリモート環境に適した考え方として注目されています。
EDRとSIEMがゼロトラスト実現に果たす役割
ゼロトラストの「常に検証・監視する」という原則は、以下の機能によって具体化されます。
- EDR:ゼロトラストの「デバイス信頼性の検証」を担う
PCやサーバーがマルウェア等に感染していないか常に監視し、デバイス自体の健全性を検証・制御します。 - SIEM:ゼロトラストの「ユーザー行動の継続的監視」を支える
組織全体のログを横断的に分析し、正規IDであっても普段と異なる不審な振る舞いを検知します。
ゼロトラスト導入におけるEDR/SIEMの位置づけ
EDRとSIEMは、ゼロトラストアーキテクチャにおける、データ収集と分析を担う「基盤」として位置づけられます。両者が提供する情報はアクセスの信頼性を評価する上で不可欠であり、その導入・連携は実現に向けた大きな一歩です。
まとめ:EDRとSIEMの適切な使い分けでセキュリティを強化
本記事では、EDRとSIEMの基本的な役割から、明確な違い、連携によるメリットまでを解説しました。EDRは「エンドポイントの深い監視」、SIEMは「組織全体の広い監視」と、それぞれ守備範囲が異なる相互補完的な関係にあります。
EDRとSIEMの特性を理解し、自社に最適なセキュリティ体制を構築することで、サイバー脅威に強い企業づくりを実現しましょう。
【ホワイトペーパー】
人材不足・複雑化する脅威にどう立ち向かう?
MDRアウトソーシングで乗り越えるセキュリティ運用の壁
ダウンロード