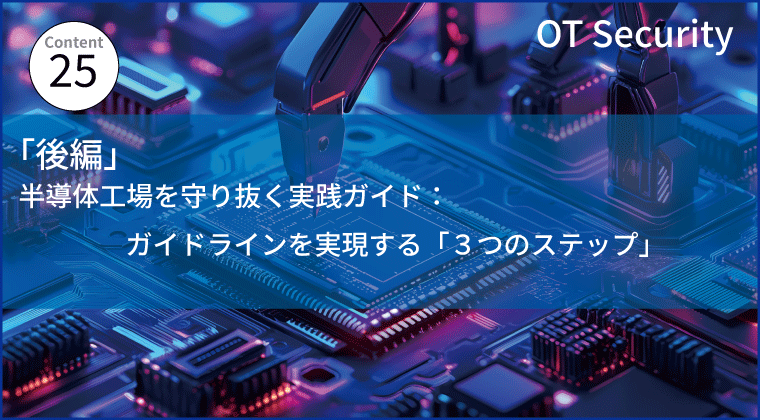インシデント対応(インシデントレスポンス)とは?
インシデント対応とは、サイバー攻撃や情報漏洩などのセキュリティインシデントが発生した際に、その被害を最小限に食い止め、迅速な復旧と事業継続を実現するためのプロセスを指します。単なる「対処」ではなく、企業の信頼と事業の継続性を守るための戦略的な防衛策です。
被害を最小化し、事業継続を守るための防衛策
インシデント対応の最大の目的は、被害の極小化と事業の継続です。初動対応のスピードと正確さが、マルウェアの拡散や情報漏洩の拡大を防ぎ、システム停止時間を短縮する鍵となります。これにより、金銭的な損失や顧客からの信頼失墜といったビジネスへのダメージを最小限に抑え、事業活動を可及的速やかに正常化させることが可能になります。
「インシデントは必ず起こる」という前提とゼロトラスト思想
インシデント対応は、「侵入されること」を前提としたアプローチです。これは「何も信頼せず、常に検証する」ことで内部での被害拡大を防ぐゼロトラスト思想と根底で通じており、現代のセキュリティ戦略において不可欠な考え方です。完璧な防御は存在しないという現実を受け入れ、インシデント発生後の検知と対応の能力を高めることが、企業の持続的な成長を支える鍵となります。
関連記事:【ゼロトラストとは?】MDRで実現する次世代セキュリティ
インシデント対応は“準備”と“初動”がすべてを左右する
インシデント発生時に、誰が、何を、どの順番で行うべきか。この問いに即座に答えられるかどうかが、被害影響の大きさを決定づけます。場当たり的な対応は混乱を招き、被害を拡大させる原因となります。事前に整備された計画と体制に基づく、冷静かつ迅速な初動対応こそが、インシデント対応の成否を分ける最も重要な要素です。
インシデント対応の全体像:対応フローの4フェーズ
効果的なインシデント対応は、国際的なベストプラクティスであるNIST(米国国立標準技術研究所)のガイドライン等で示される、標準化されたフローに沿って行われます。このプロセスは「準備」「検知と分析」「封じ込め・根絶・復旧」「事後対応」の4つのフェーズで構成されており、それぞれが連携して機能することで、被害の最小化と再発防止が可能になります。
フェーズ1:準備(Preparation)
インシデント発生に備え、事前に行うすべての活動がこのフェーズに含まれます。
- 体制の構築: CSIRTなどの専門チームを設置し、役割と責任を明確化する。
- 計画の策定: インシデント対応計画(IRP)を作成し、連絡体制や対応手順を文書化する。
- ツールの導入: EDRやSIEMなど、検知・分析に必要なツールを配備する。
- 訓練の実施: 定期的な訓練を通じて、計画の実効性を検証し、担当者のスキルを維持・向上させる。
- 活用される技術・体制: 平時からCSIRTが中心となり計画を策定。EDRやSIEMを活用して、検知できる体制を整えておく。
フェーズ2:検知と分析(Detection & Analysis)
インシデントの発生を検知し、それが実際にセキュリティインシデントであるか、どのような影響があるかを分析・評価するフェーズです。
- 検知: SIEMやEDRからのアラート、ユーザーからの報告などからインシデントの兆候を掴む。
- 分析: ログを分析し、攻撃の手法、影響範囲、緊急度などを評価・特定する。
- 報告: 事前に定めたルールに従い、責任者や経営層へ状況を報告する。
- 活用される技術・体制: SIEMやEDRが発するアラートを検知の起点とする。専門家が24時間体制で監視するMDRサービスは、このフェーズで特に大きな価値を発揮する。
フェーズ3:封じ込め・根絶・復旧
インシデントによる被害の拡大を阻止し、原因を排除して、システムを正常な状態に戻すフェーズです。
- 封じ込め: 感染した端末をネットワークから隔離するなど、被害の拡大を食い止める。
- 根絶: マルウェアの駆除や、不正に作成されたアカウントの削除など、インシデントの根本原因を取り除く。
- 復旧: クリーンなバックアップからのリストアや、システムの再構築を行い、サービスを正常な状態に戻す。
- 活用される技術・体制: EDRの遠隔操作機能により、迅速な端末隔離・封じ込めを行う。CSIRTが全体の指揮を執り、復旧作業を進める。
フェーズ4:事後対応(Post-Incident Activity)
インシデントが収束した後に行う、一連の振り返りと改善活動のフェーズです。
- 報告書の作成: インシデントの概要、対応内容、被害状況、原因などをまとめた報告書を作成する。
- 原因分析と再発防止: なぜインシデントが発生したのかを深く分析し、恒久的な再発防止策を策定・実施する。
- プロセスの改善: 今回の対応における課題を洗い出し、インシデント対応計画や体制を見直す。
- 活用される技術・体制: CSIRTが中心となり、SIEMやEDRのログを基に原因を深く分析し、再発防止策を策定。得られた知見を「準備」フェーズにフィードバックする。
インシデント対応を支える多様な技術と体制
効果的なインシデント対応は、最適な技術と明確な体制によって支えられます。ここでは、インシデント対応の各フェーズで重要な役割を果たす主要な技術と、その中核となる組織体制について解説します。
技術編
MDR (Managed Detection and Response)
専門家が24時間365日体制で監視を行い、インシデントの検知から分析、初動対応までを代行するサービス。人材不足を補い、対応の質と速度を向上させる。
EDR (Endpoint Detection and Response)
PCやサーバーの挙動を監視し、不審な活動を検知・記録するツール。遠隔からの端末隔離など、迅速な封じ込めを実現する。
SIEM (Security Information and Event Management)
組織内の様々な機器からログを収集・相関分析し、インシデントの兆候を早期に検知するプラットフォーム。
SOAR (Security Orchestration, Automation and Response)
事前に定義した手順(プレイブック)に基づき、インシデント対応プロセスの一部を自動化するツール。
体制編
CSIRT (Computer Security Incident Response Team)
インシデント発生時に、組織内の司令塔として対応全体の指揮を執る専門チーム。関係各所との連携や情報集約の中核を担う。
インシデント対応の構築方法
CSIRT(シーサート)の設置と役割の明確化
インシデント対応体制の要は、専門部隊であるCSIRTの設置です。平時からインシデントに関する情報を収集・分析し、有事の際には現場の対応を指揮します。経済産業省のガイドラインでも、その重要性が指摘されています。
“影響範囲や損害の特定、被害拡大防止を図るための初動対応、再発防止策の検討を適時に実施するため、制御系を含むサプライチェーン全体のインシデントに対応可能な体制(CSIRT 等)を整備させる。”
引用元:経済産業省「サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver 3.0」
https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/guide_v3.0.pdf
インシデント対応計画(IRP)に盛り込むべき項目
CSIRTが行動の指針とするのが、インシデント対応計画(IRP: Incident Response Plan)です。これには、対応の精度とスピードを高めるための具体的な項目を盛り込む必要があります。
- インシデントの定義と深刻度判断基準
- CSIRTの役割、責任、権限
- インシデント発生時の報告・連絡体制(経営層や関係部署へのエスカレーションルール)
- 各フェーズにおける具体的な対応手順
- 外部専門家(弁護士、フォレンジック調査会社など)との連携手順
計画を形骸化させないための定期的な訓練
どれだけ優れた計画も、訓練されていなければ「絵に描いた餅」です。特定のシナリオ(例:ランサムウェア感染)を想定した机上訓練や、実際にシステムの一部を動かす実践的演習などを定期的に実施し、計画の実効性を確認するとともに、担当者の対応能力を高めることが不可欠です。
多くの企業が陥るインシデント対応の落とし穴
多くの企業がインシデント対応体制を整備しようと試みますが、いくつかの共通した課題によって、その実効性が損なわれるケースが少なくありません。ここでは、企業が陥りがちな代表的な落とし穴を3つ紹介します。
- インシデントの検知・報告体制が不明確:
従業員が不審な挙動を発見しても、「誰に、何を、どのように」報告すればよいか分からず、初動が大幅に遅れるケース。 - 経営層の理解不足と判断の遅れ:
セキュリティをIT部門任せにし、インシデントの事業インパクトを理解していない経営層が、システムの停止や顧客への公表といった重要な意思決定をためらい、被害を拡大させるケース。 - 専門知識・スキルを持つ人材の不足:
ログの解析やマルウェアの特定など、高度な専門知識を持つ人材が社内にいないため、原因究明や適切な対処ができずに事態を悪化させるケース。
まとめ:インシデント対応の成否は「事前準備」で決まる
サイバー攻撃によるインシデントは、すべての企業が直面しうる経営リスクです。インシデントが発生した際に、その被害を最小限に抑えられるかどうかは、どれだけ周到な「事前準備」ができていたかによって決まります。
実効性のあるインシデント対応体制を構築するには、CSIRTのような「体制」、EDRなどの「技術」、そして定期的な「訓練」という3つの要素をバランス良く揃えることが鍵となります。また、専門人材の不足が深刻な課題となる中、24時間365日体制で高度な知見を提供するMDRサービスのような外部支援を積極的に活用する事も、事業継続を守る上で重要な戦略と言えるでしょう。
【ホワイトペーパー】
人材不足・複雑化する脅威にどう立ち向かう?
MDRアウトソーシングで乗り越えるセキュリティ運用の壁
ダウンロード