
臨時レポート 2025年8月7日
クルド人グループによる日本の組織を狙ったサイバー攻撃
Security Knowledge

クルド人グループによる日本の組織を狙ったサイバー攻撃

近年では企業のオフィスだけでなく、工場のような生産現場においても、業務効率化のためにDXを推進する動きが活発です。本来、工場DXとOTセキュリティ対策は両輪で進めるべきですが、OTセキュリティ対策に関しては優先度が低いと考えている企業も少なくありません。 本コラムでは工場DXを推進していた製造業B社のケースを紹介します。B社では、ある日突然、工場の機器が一斉に停止しました。前編では、操業停止から再開までの3週間に起こったことと、その影響について説明します。

工場の管理者にとって、絶対に避けたい事態とは何でしょうか?多くの方が、意図せぬ品質不良や労災事故、操業停止などを思い浮かべるのではないでしょうか。安全対策として、5S、KYT、ヒヤリハット活動などに取り組んでいる企業も少なくありません。 しかし近年、工場に求められる安全対策が変わりつつあります。そのため、多くの企業で、一部の重要な安全対策が見落とされ、手つかずになっています。このまま放置すれば、深刻な事故にも発展しかねません。「見落とされている安全対策」とは、いったいどのようなものでしょうか? 本コラムでは、工場の安全対策を強化したい方、より万全な安全対策を知りたい方に向けて、これからの時代に不可欠な工場の安全対策を解説します。

企業のセキュリティ対策において、「SOC」と「SIEM」という言葉を耳にするようになりました。両者は混同されがちですが、効果的なセキュリティ運用体制を築く上でその本質的な違いと連携のポイントを把握することは、不可欠です。本記事では、SOCとSIEMの根本的な違いを明確にし、連携方法、さらに最適な監視体制を構築するための実践的なヒントもご紹介します。

近年はIoT化やスマートファクトリー化の流れの中で、OTシステム(工場の制御システム)が直接、もしくは連携している情報システム(IT)を介して外部ネットワークに接続されるようになり、サイバー攻撃のリスクが増大しています。OTシステムがサイバー攻撃を受けた場合の被害は甚大で、作業員の安全が脅かされる可能性や、生産活動そのものが重大なダメージを受ける可能性もあります。 本コラムでは、OTシステムにどのようなセキュリティリスクがあるのか詳しく解説します。その上で、OTセキュリティ対策を何から始めたらいいかわからないとお悩みの方向けに、今すぐWebで実施できるOTセキュリティ簡易診断について紹介します。

近年では工場のDX化が推進され、OTシステムと情報システム(IT)の連携や、OTシステムにおけるクラウドサービスの利用が増えています。また、リモートワークの浸透により、OTシステムでもリモート接続による保守作業が行われるようになりました。このように、OT環境が外部に向けて開かれるようになったことで、工場におけるサイバー攻撃のリスクが増大しています。しかし、ITセキュリティ対策と比較すると、OTセキュリティ対策は進んでいない企業が多いのが実情です。
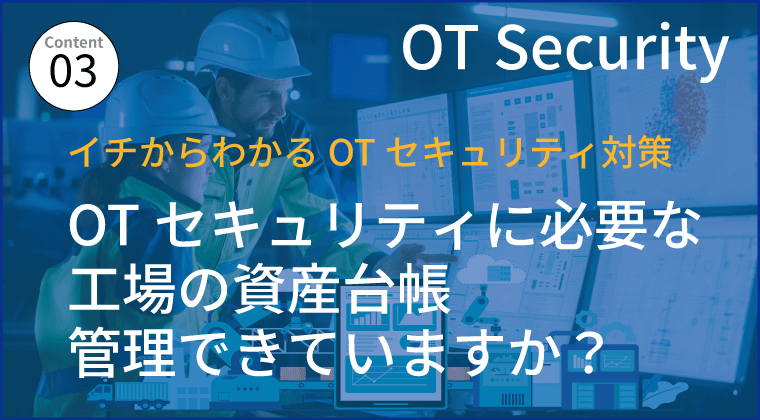
工場の資産とは、どのようなものだと思いますか?生産ラインの機械や搬送装置、事務所の棚や机などのいわゆる「固定資産」をイメージする方も多いのではないでしょうか。 本コラムで取り上げる工場の資産は、経理目線での固定資産という意味ではなく、OTシステム(工場の制御システム)の構成要素のことです。ネットワーク機器やサーバー、PCなどはもちろん、生産ラインの機器や自動搬送装置(AGV)なども含まれます。また、OSやソフトウェアも資産です。工場をサイバー攻撃から守るためのOTセキュリティ対策において、こうした資産を一覧化して管理することは非常に重要です。

OTシステム(工場の制御システム)へのサイバー攻撃のリスクが増大しているため、情報セキュリティの観点から工場の現状把握と評価を行う必要性が増しています。

OTセキュリティ、何から始めて、どう進めるべきか、3つのステップで、わかりやすく解説します
Inquiry
お客様の業務課題に応じて、さまざまなソリューションの中から最適な組み合わせで、ご提案します。
お困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。